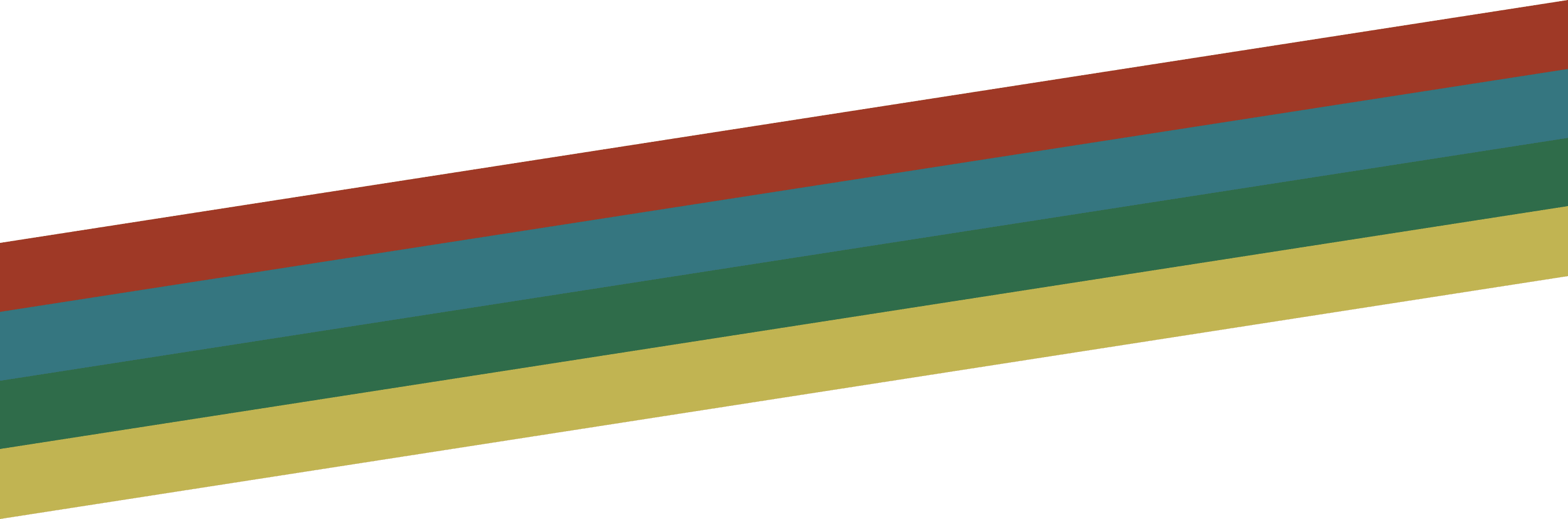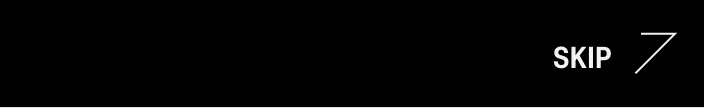

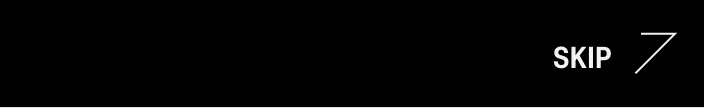


ものに愛着を持ち、変化を味わう。
背景を想い、過ごした時を感じる。
見る、思う、味わう、そしてつくる。
わたしたちはそんな、「味わう暮らし」
をみなさまと共につくります。
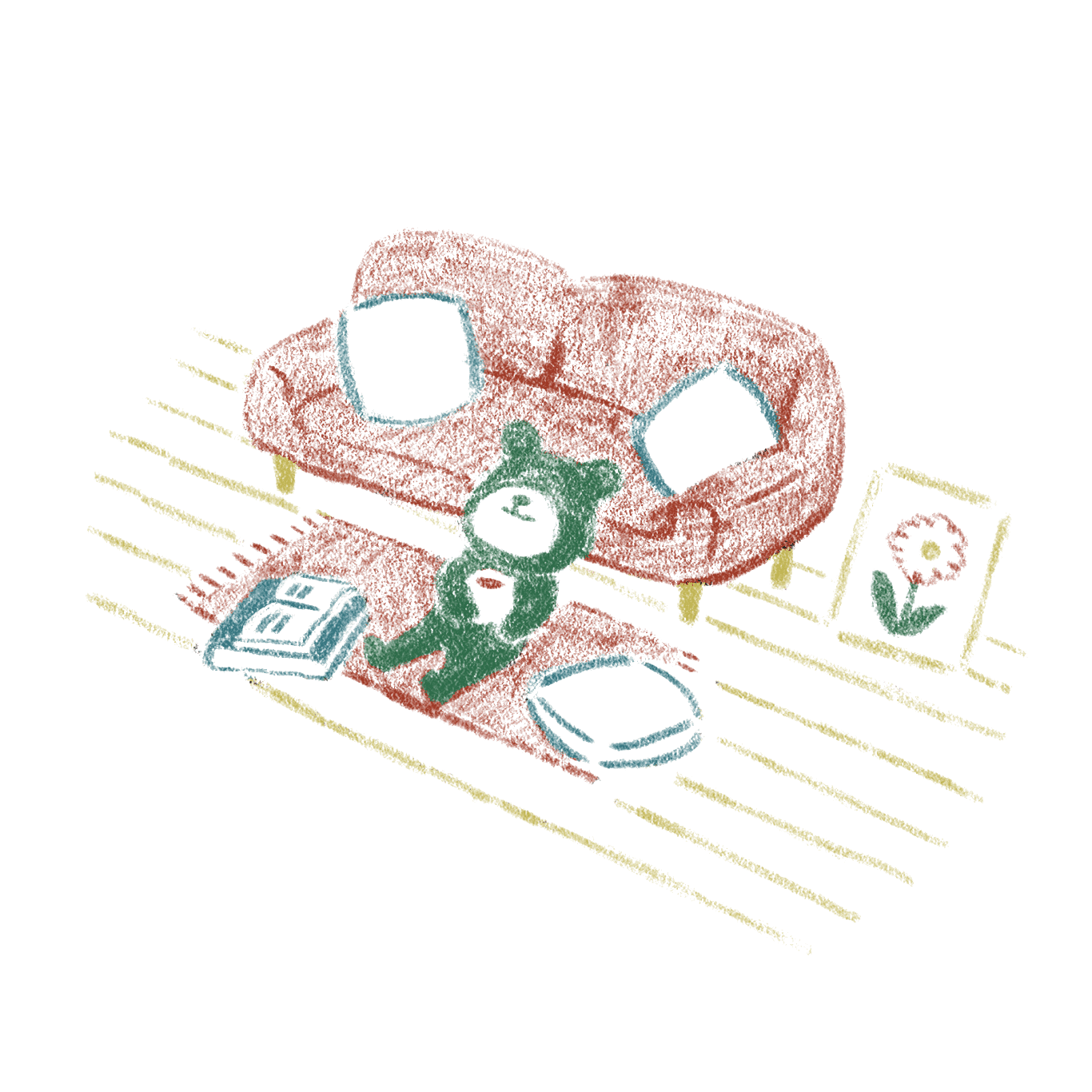
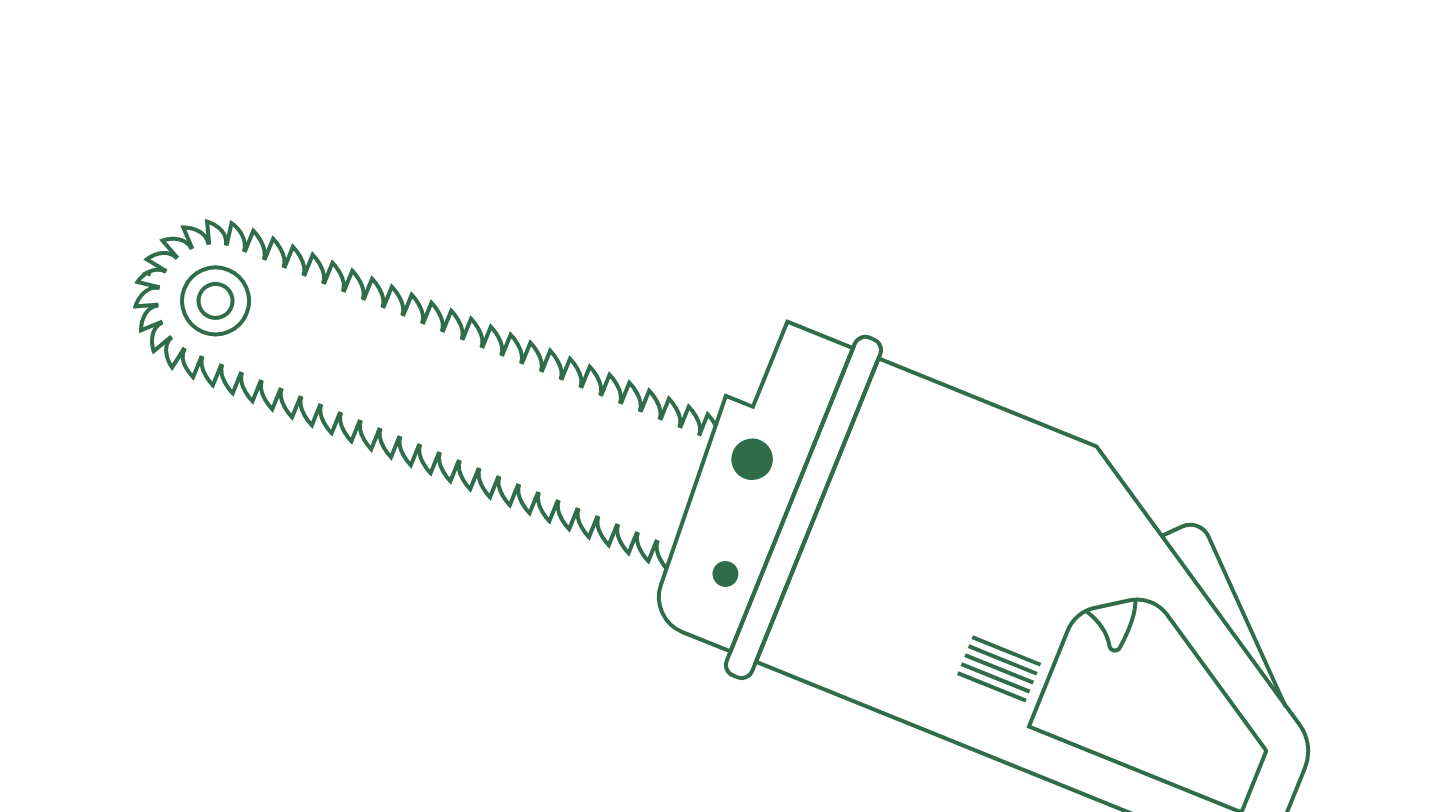
定番からオリジナルまで。
熊野の土地で取れた木を活かし、
一貫生産でつくり上げるnojimokuの製品。

製材も熊野も、もっと楽しく、おもしろく。これまで製材業として製品作りを追求してきたnojimokuの、さまざまな企画が一挙に見られるのじもくプロジェクツ。あんなところやこんなところにも、製材の魅力が活きる楽しい企画が生まれています。次にnojimokuと楽しい企画を始めるのは一体・・・!
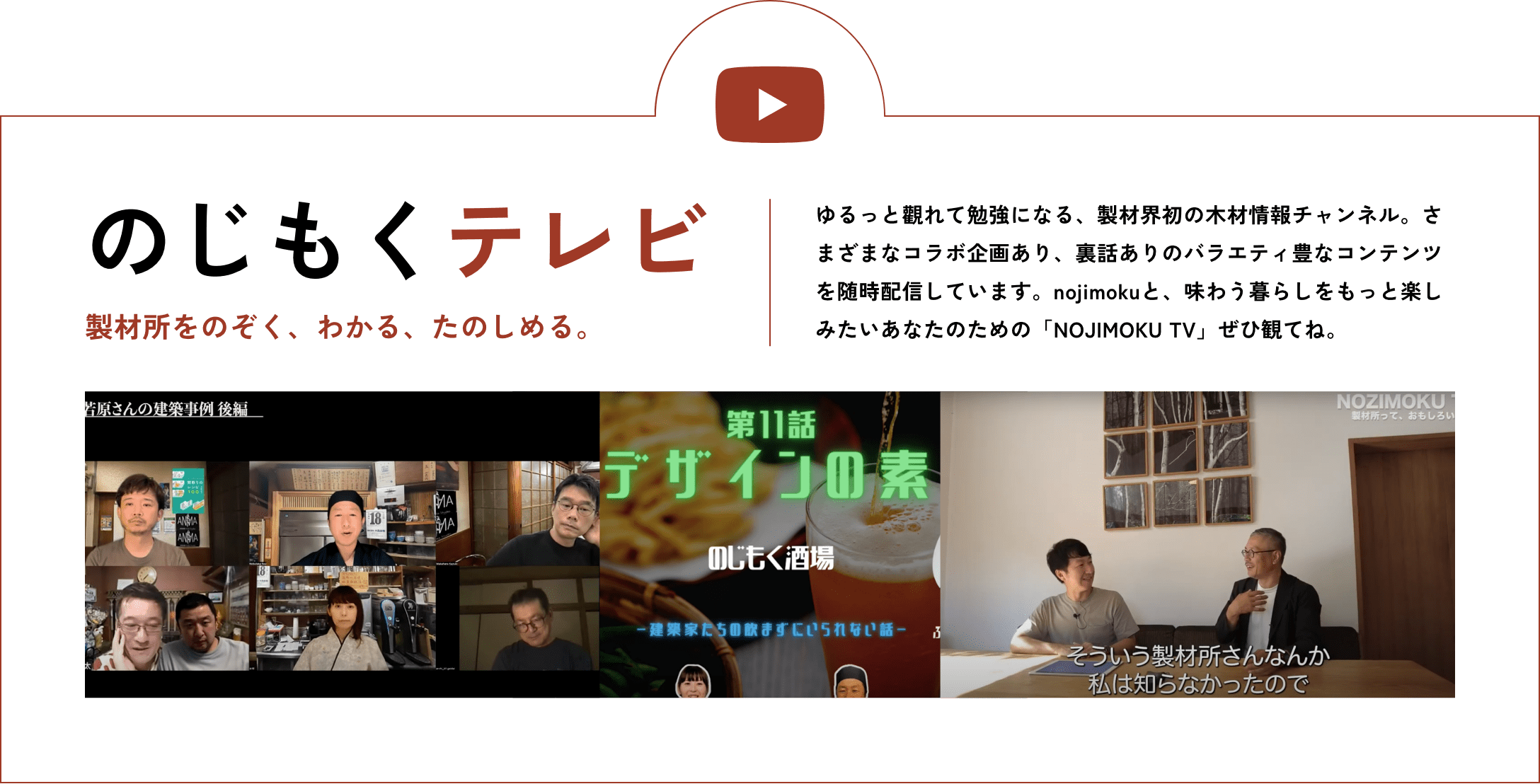
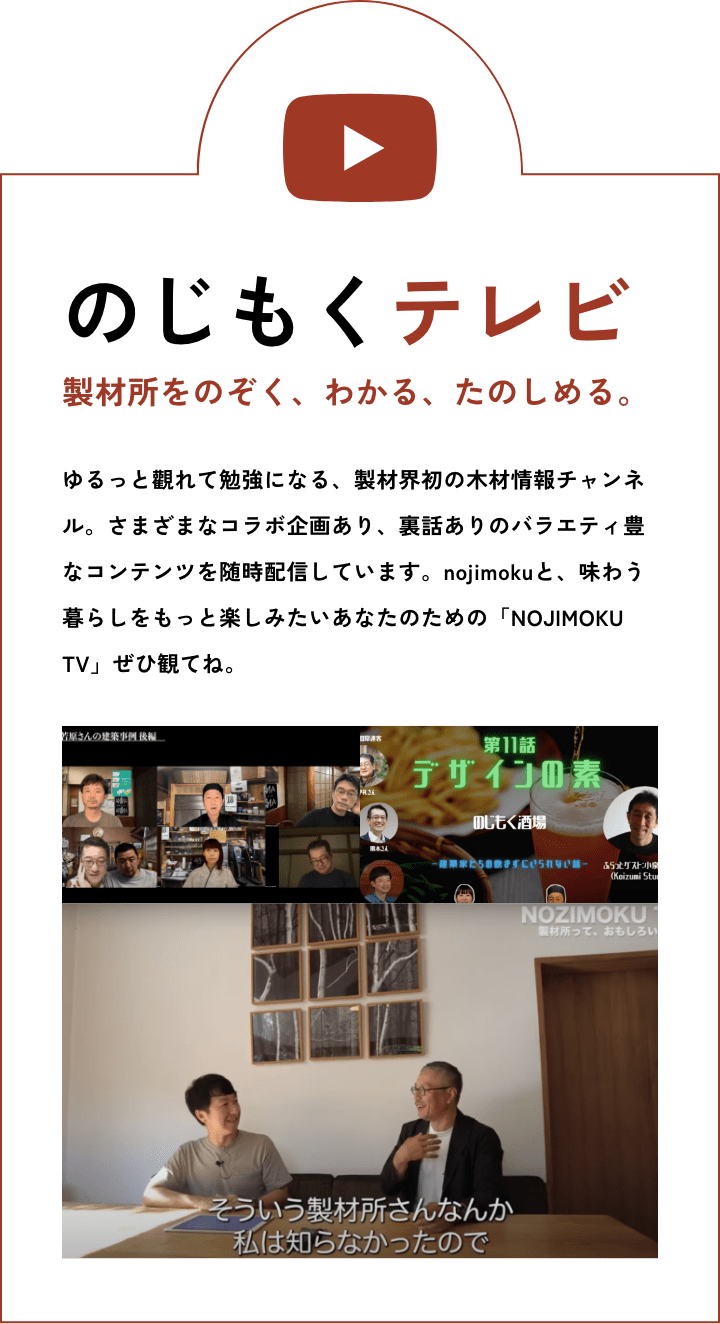
野地木材工業はこのたび、社名をnojimokuに改め、これまで以上に変化を楽しみ、前進するため生まれ変わります。「nojimoku」というシンプルな名前に込めた、製材の基礎を再認識する姿勢と、未来へ向かってどこまでも広がっていこうという意気込みを、事業を通して表現します。私たちは、変化の激しい現代の中にいて、変わらず独自の時を歩む「木」とだからこそつくれる未来があると信じています。木とともに、暮らしを味わう未来を。
木が好きな人、ものづくりが好きな人、寡黙な人、おしゃべり好きな人、長く働きたい人、生活とのバランスを取りたい人…。
木が好きな人、ものづくりが好きな人、寡黙な人、おしゃべり好きな人、長く働きたい人、生活とのバランスを取りたい人…。
木が好きな人、ものづくりが好きな人、寡黙な人、おしゃべり好きな人、長く働きたい人、生活とのバランスを取りたい人…。
木が好きな人、ものづくりが好きな人、寡黙な人、おしゃべり好きな人、長く働きたい人、生活とのバランスを取りたい人…。